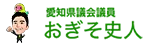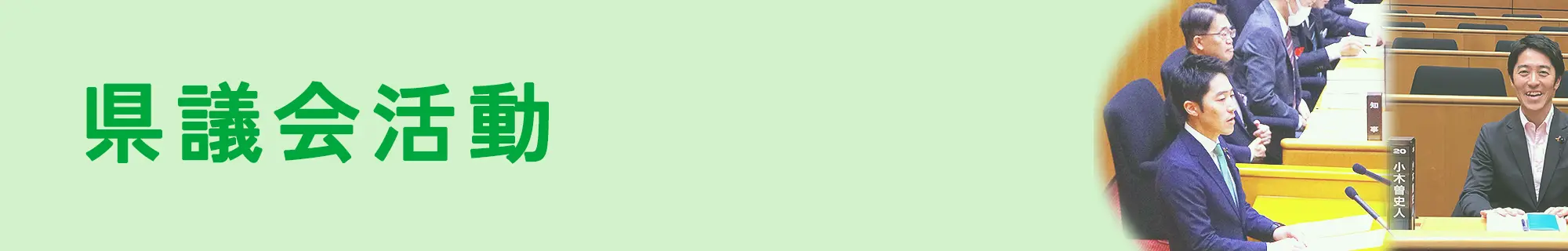

令和6年9月定例会(第4号) 本文 2024-09-27
◯二十番(小木曽史人君)
通告に従い、私からは大きく三項目について順次質問をいたします。
初めに、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた取組についてです。
愛知県の県内総生産は東京、大阪に次ぐ第三位、製造品出荷額等は約四十七兆円で四十五年連続日本一と堅調に見えるものの、グローバルに見れば、日本の成長はここ数年、足踏みを続け、足元では、愛知県の屋台骨と言われる自動車産業をはじめとするモノづくり産業も大転換を求められる時代となってきているのは周知の事実です。
そんな中、愛知県の成長戦略の起爆剤として期待されるのがスタートアップ・エコシステムの形成であり、Aichi─Startup戦略を基軸として、毎年新たな取組を進めていると承知をしております。
ここでは、STATION Ai開業を目前に控えたこの時期に、細かな具体的施策というよりは、改めて大局的な見地から、スタートアップ・エコシステムの形成における県の取組姿勢についてお聞きをしていきたいと思います。
まず、忘れてはならないのは、スタートアップの推進は、あくまで愛知県、ひいては中部圏域の成長戦略の中の一つの手段、アプローチであるということです。
例えば福岡では、産学官民で組成された福岡地域戦略推進協議会、通称FDCが福岡県域の成長戦略の策定から推進までを一貫して行う第三者的な統括機関として機能し、このFDCが司令塔となって、そこにスタートアップの成長が位置づけられ、公共政策との連動、企業の新規事業創造のための具体的施策が複合的に推進されるという仕組みを取っております。
本県においても、愛知県及び中部圏域の国際的な産業競争力を高め、地域産業基盤を底上げし、持続的な成長を遂げるために、スタートアップをどう支援し、成長させるべきかといった俯瞰的な捉え方を常に意識することが重要であると考えます。
そこで、まずは愛知の産業全体の成長戦略においてスタートアップ・エコシステムをどのように位置づけているのか、また、愛知県のスタートアップ・エコシステムの現状と課題についてお伺いをいたします。
来月オープン予定のSTATION Aiは、スタートアップ・エコシステムの中核拠点となるべき施設であり、私もこれまで様々、スタートアップに関わる方々にお会いし、総じて大いに期待しているとの声を伺っております。その期待感に応え、愛知が選ばれる場所となるために、スタートアップを取り巻くあらゆるステークホルダーを集積する、的確かつ効果的な環境を整備する必要があります。
それは、例えば、スタートアップ側から見れば、成長のための伴走支援を含めた充実したメンタリング、魅力的なマッチングプログラム、法人住民税の免除等のインセンティブ、スタートアップしやすい実証フィールドの存在などであり、そこにオープンイノベーションがマインドセットされた多くの既存企業の積極的な参画と十分な資金調達のしやすさといった環境です。
こうした環境整備を進めるために、愛知県では既に一昨年四月にプレ・ステーションAiの運営を開始し、多くの取組が進められてきていると承知をしておりますが、重要なのは、STATION Aiがスタートアップ・エコシステム形成における世界に誇るインキュベーションとなるために、二年間の運営の中で得られた成果を継続させるとともに、明らかとなった課題を解消していくことであると考えます。
そこで、約二年間運営されたプレ・ステーションAiで得られた成果と課題をどのように認識し、今後のSTATION Aiを中核としたスタートアップ・エコシステムの形成にどのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。
質問に当たり各方面へヒアリングを行う中で、愛知初のスタートアップ・エコシステムの成功の鍵はとの問いに対しては、皆さん、口をそろえて、モノづくりとの連携と融合で一致をしておりました。特に、ディープテック系スタートアップを牽引し、ロールモデルを多数輩出してほしい、ディープテックの中でもAIやコンピューターサイエンス分野は競争が激化しており、世界に後れを取っている現状から、独自の強みでもあるモノづくりを生かした材料技術、つまり、マテリアル系ディープテックの輩出に期待する声が多く聞かれました。
スタートアップは先進的な技術と素早さを備え、一方、既存の県下モノづくり企業は安定した品質と規律が取れた体制を持っています。その二つがうまく融合された形を取れれば、大きな成果が生まれる可能性が芽生え、そこにその期待感を持った新たな投資環境が生まれるといった好循環、まさに愛知初の差別化されたスタートアップ・エコシステムが生まれるのではないかと考えます。
モノづくりとの融合の新たな形としては、例えば、世界的に見ると、スタートアップを投資の対象としてだけではなく、クライアント、顧客として協業するビジネスモデル、いわゆるベンチャークライアントモデルが生成され、BMWやシーメンス、エアバスなど多業種で活用が始まるなど、スタートアップという外部のアイデアや技術を積極的に取り入れようという、まさにオープンイノベーションとしての動きが加速をしております。
しかしながら、愛知県には最先端かつ高度なモノづくり産業が集積しているものの、オープンイノベーションの掛け声とは裏腹に、スタートアップと融合した具体的なビジネスモデルをなかなか創出できない状況があるともお聞きをしております。
STATION Aiには多くのモノづくりのパートナー企業が入居すると伺っておりますので、世界トレンドに後れを取らないようなオープンイノベーションへのマインドチェンジを促す流れをぜひつくっていただきたいと思います。
そこで、Aichi─Startup戦略の中でも掲げられているモノづくり融合型の愛知県独自のスタートアップ・エコシステムの形成について、現状課題をどう認識し、今後どのように進めていくのかお伺いをいたします。
愛知初のスタートアップ・エコシステムの形成に向けて、もう一つ忘れてはならない視点がダイバーシティーです。
海外スタートアップの誘引の視点からは、世界標準のダイバーシティーの感覚があらゆる人や文化を集積する原動力となり、それが課題に対するアプローチを多様化し、革新的なビジネスモデルを生み出す源泉となります。
また、女性活躍の視点から言えば、魅力的な職場環境や賃金ベースが高い首都圏に多くの若年女性が転出している愛知県の現状に対し、例えば、今後、首都圏でスキルを身につけた若年女性が起業したいと考えた場合に、STATION Aiを含む愛知県のスタートアップ・エコシステムの中に魅力的な環境や支援メニューを提示できれば、それをキャッチアップできる可能性もあるのではないかと考えます。
STATION Aiが目指すべき目標としている世界最大のインキュベーション、ステーションFも、女性創設者フェローシップや、ファイターズプログラム等、女性や恵まれない環境を持つスタートアップに特化したプログラムや支援を積極的に展開しているように、ダイバーシティーを具体的に体現した形をSTATION Aiから強く発信していくべきと考えます。
そこで、STATION Aiにおけるダイバーシティーの取組についてどのように考えているのか、また、スタートアップの世界で女性が活躍するために愛知県としてどのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。
次に、大規模災害への備えとして、主に三点、問題提起を含め、これからの県の対応について順次質問をしていきます。
質問に先立ちまして、先日、能登半島を襲った記録的豪雨、私たちに震災後の二次被害の恐ろしい現実を突きつけたわけでございますが、まずは失われた貴い命に対し心から御冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。
さて、能登半島地震では、市町村の設置した指定避難所への避難者だけでも、一月二日に最大の四万六百八十八人、九月二十四日現在もなお、三市町村二十四か所の避難所に二百四十九人の方が避難されていると伺っております。
避難所生活については、トイレ等の劣悪な衛生環境、精神的なストレスによる健康悪化、プライバシー確保のほか、災害備蓄品の機能性の問題、ペット問題、食物アレルギー対応など、新たな課題も浮き彫りとなり、日本特有の課題とも言われる災害関連死が報道等で再びクローズアップされ、避難所のQOL向上を求める声はこれまでにないほど高まっております。
一方で、避難所に避難しなかった方、いわゆる在宅避難や車中泊避難といった避難所外避難をした方も大勢いらっしゃり、実際に、支援の手が届かず健康状態が悪化し、ひいては命を落とした方も少なくありません。
ちなみに内閣府の資料によると、熊本地震では、車中泊避難経験者が七四・五%、また、在宅避難経験者が五〇・九%にも上り、災害関連死も避難所滞在中と比較して、自宅等で高い比率で発生していることが報告をされております。
キャパシティーの限界で避難所に入れない方、家族や自分の健康状態で自宅から出られない、余震が怖くて建物の中に入りたくない、乳幼児を抱えており泣き声が気になるなど、現実問題、個々人の様々な事情で避難の在り方は多様化しているため、被災者への支援の考え方を場所の支援から人の支援にシフトし、避難場所にかかわらず、必要な人に必要な支援が届くような在り方を考える必要があります。
こうした背景から、本年六月には内閣府から、在宅・車中泊避難者等の支援の手引きが発出されております。地域防災計画への明確な位置づけ、デジタル技術を活用した被災者情報の把握と的確かつタイムリーな情報発信、相談窓口機能を備えた支援交流拠点の設置、具体的な物資の配付方法、衛生・健康管理、訓練の在り方など、避難所で求められる支援と同水準、同程度の支援をいかにして在宅、車中泊を含む避難所外避難者に届けるか。そのオペレーションは簡単ではなく、通常の避難所運営よりも高度な、民間支援団体を含めた関係機関との連携と体制づくりが求められると考えます。
そこで、まずお伺いをいたします。
大規模災害時の在宅・車中泊避難者への支援に対する課題を県としてどう認識しておられるのか。また、国の手引を踏まえ、在宅・車中泊避難を行う被災者にも支援が行き届くようにするために、県として今後どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。
次に、専門的な技能を持つNPOや企業、団体等のボランティア団体、以下、専門ボランティア団体と申し上げますけれども、この専門ボランティア団体による被災地支援の体制構築についてお伺いをいたします。
災害時のボランティアによる支援活動には、個人ボランティアによる被災住宅のごみや瓦礫の搬出、家財の片づけといった支援のほか、専門ボランティア団体による避難所での炊き出し、支援センターの運営、重機を活用した作業などの被災者のQOLを高める支援が不可欠で、能登半島地震でもその専門性とノウハウやスキルを生かした迅速かつ献身的な取組のおかげで救われた方が大勢いらっしゃいます。
こうした専門ボランティア団体の活動が災害時における大きな支援の力として注目されたのが熊本地震です。
熊本地震では、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)が専門ボランティア団体の情報共有会議を開催し、情報や課題の共有をはじめ、避難所や災害ボランティアセンターの運営支援、支援物資の供給、炊き出しなど、多様な支援活動が行われました。
その後、熊本県では、災害中間支援組織として機能するくまもと災害ボランティア団体ネットワークが設立されて、専門ボランティア団体の相互調整、行政との連携、企業からの支援の調整等が行われたと伺っております。
本県においても、南海トラフ地震等大規模災害では被害が甚大かつ広域にわたると想定され、市町村の災害ボランティアセンターの体制によっては、被災地支援に濃淡が出ることも当然予想されます。
そうした際に、いわゆる専門ボランティア団体が十分に力を発揮するためには、全国各地からの専門ボランティア団体のハブとして、県下被災地の的確なニーズマッチングを含めた効率的かつ効果的な支援につなげる活動支援と情報共有・活動調整機関として機能する災害中間支援組織の役割が大いに期待されるところであり、その体制づくりを早急に進める必要があると考えます。
そこでお伺いをいたします。
大規模災害発災時に想定される専門ボランティア団体の受入れに関する課題認識、そして、災害中間支援組織と行政及び市町村の災害ボランティアセンター等関係機関との連携体制の構築について、県として今後どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。
最後に、四月下旬、能登半島へ炊き出し支援と現地調査に伺った際に話題となった避難所の出口戦略について伺います。
ある自治体では、コミュニティーごとに組成された一時的な生活場所としての避難場所が社会的要請であるQOLの高まりも相まって、不自由のない居心地のよい生活拠点となってしまい、避難所をなかなか閉じられないという本音を伺いました。
一方で、ある自治体の小さな地区では、顔の見える関係を長年築いてきた地区の代表者が指定避難所の避難者に対し、自宅等のライフラインの復旧のめどがついた段階で、それぞれ置かれている状況や悩みなどを丁寧にお聞きしながら、自立生活のフェーズに移行できるよう行政とも相談しつつ、真摯に粘り強く避難所退去を促し、発災後三か月以内で避難所を閉鎖したというお話を伺いました。閉鎖に当たっては、その地区の中に支援交流センターを立ち上げ、相談支援を行う専門ボランティア団体による運営を継続するなど、配慮もなされておりました。
もちろん、個別の様々な事情から、避難所をなかなか出られない被災者もおられるわけで、そういった方への支援やケアは最優先で考えるべきであることは言うまでもありません。
ただ、発災から一定期間が経過すると、指定避難所となっている施設、例えば学校や地域の公民館や公共施設等を本来の役割に戻す必要が出てきますし、地域のいち早い復旧・復興を成し遂げるには、避難所の閉鎖は避けては通れず、事前の構えとして、避難所の出口戦略について、地域の防災計画や避難所運営マニュアル等に避難所の考え方や懸念事項や方策の一例を示すなどの対応が必要なのではないかと感じたところです。
そこでお伺いをします。
避難所の閉鎖等出口戦略は、基本、市町村の判断によるものと承知をしておりますが、県としてもある程度、事前の構えとして、避難所の閉鎖を見据えた基本的な避難所の出口戦略を示す必要があると考えますが、県の考え方を伺います。
続いて、児童虐待への対応について伺っていきます。
愛知県における児童相談センターへの虐待相談件数は年々増加しており、二〇一九年度には年間六千件を超え、直近の二〇二三年度は年間七千七十三件と、十年前の約三倍に上っています。
もちろん、この数字は必ずしも悲観的な数字ではなく、近年、児童虐待に対する社会的関心が高まったことで、児童虐待死の危険性を周囲が感知し、警察を含め、通報がしやすくなった環境が広がり、これまで届かなかった子供たちの悲痛な叫びを拾い上げ、救うことにもつながっていると考えることもできます。
ただ、それでも救えなかった命があるという現実があります。
本県でも本年五月、犬山市で七歳の小学一年の女児が、児相での一時保護解除後に実母の内縁の夫に暴行を受け、命を失うという大変痛ましい事件がありました。
こうした報道を耳にするたびに、なぜ救えなかったのか、やりきれない思いでいっぱいになります。
個別具体的な事案についての対応いかんについては、今後の検証結果を待ちたいと思いますので、ここでは児童虐待死につながる可能性が高い一時保護事案を念頭に、実際に事案に直接対峙する、いわゆるケースワークを充実させるための体制と、親から分離された子供を守るための環境整備という角度で質問をしていきます。
本県では、近年の児童虐待相談対応件数の増加に伴い児相職員数を大幅に増加し、あわせて児童福祉司や児童心理司等の専門職員も増員するなど、ケースワークをする人的リソーセスを拡充することで、子供や親への支援を効果的に実施できる体制を強化してきていると承知をしております。
同時に、親と引き離して一時的に保護する一時保護措置事案も増加しており、二〇二三年度は千五百二件に上ります。
一時保護所として利用される社会資源としては、県立の一時保護施設が二施設七十八名受入れ可能、児童養護施設や乳児院に適切な受入れ体制が整備されていることを前提として設置されている一時保護専用施設が七施設四十名受入れ可能、その他、養育里親への一時保護などがあります。
一時保護は、子供の安全上必要な当然の措置である反面、児相判断で親子の密接な共同生活を含めた関係性を一時的にでも強制的に切り離すもので、児相及び一時保護所は、親と子供両者に対してより丁寧な対応が求められます。
ここで児相職員と一時保護所の職員の役割を少し整理しておきます。
児相職員は、主に子供やその家庭に関するケースワークを担当します。子供や家庭の状況を詳細に評価し、一時保護判断を含めて子供にとって最善の保護措置を判断し、適切な支援計画の策定などを行う、必要な医療機関や教育機関、福祉サービスと連携し、子供や家庭への支援の調整を行うなどが主な役割です。
一時保護所の職員は、児相からの要請を受けて、子供たちの一時的なケアを提供する役割を担います。安全確保のための見守りのほか、具体的には衣食住の提供や日常的な生活指導を行うなど、心理的に大きな負荷を抱える子供たちに寄り添いつつ、心のケアを行います。
要するに、児相職員が計画を立て、一時保護所の職員がその計画の実行をサポートする。一時保護状態の子供に一番身近に接する一時保護所の職員が子供たちの様子や心理的な変化を児相職員に報告し、それを基に児相職員が今後の対応策を修正していく。こうした明確な役割分担と緊密な連携の中で、子供が守られるわけです。
逆に言えば、日常の連絡や報告がスムーズに行われないと、対応が遅れたり適切なケアが提供されないことになってしまいます。
先ほど述べたように、職員の人的リソーセスは年々拡充しており、個別ケースワーク対応をきめ細かに実施する環境は整いつつありますが、その対応力の差がその後の親子関係の再構築等の予後を差配する可能性があることを考えると、特に、若手職員等の経験不足ときめ細かな対応をするためのスキルアップが課題であるように思います。
そこで、まずはケースワークを充実させるため、近年の採用増により経験の浅い職員が増加していることを踏まえ、児相職員と一時保護所の職員の人材育成と連携について、県としてどのように認識し、今後どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。
次に、一時保護所の環境整備についてですが、先ほど来、述べてきたように、児童虐待から子供を守るというのは、単に危機的状況から隔離することではありません。親と切り離され、全く見ず知らずの環境に置かれる子供の不安感は計り知れず、強烈な精神的ストレスを抱えていることは容易に想像できます。
特に一時保護状態が長期にわたる場合には、その環境が子供の人格形成や発達に大きな影響を及ぼすとも考えられるため、例えば、持込み所持品の緩和、リラックスできるプライバシーが確保された適切な空間、いつでも話を聞いてもらえる大人の配置など、安心して生活できる環境を整えることがとても大切だと考えます。
これに関し、国は本年四月の改正児童福祉法施行に合わせて、新たに一時保護施設の設備及び運営に関する基準を発出いたしました。これまで一時保護施設は児童養護施設の設備運営基準を準用していたところを、一時保護は先ほど来、申し上げました、より手厚い対応が必要であることから、さらに踏み込んだ新たな基準が必要であることから策定されたと理解をしております。
県は、県立の一時保護所において専門職員を増員して夜間の受入れ体制を強化したり、教員OBを学習指導員として配置するなど、保護された子供に配慮した支援の充実や環境整備に取り組んできたとお聞きをしております。
今回の補正予算では、一時保護所に入所する児童の環境改善と受入れ体制の強化を図るため、三河地区の県立一時保護所の移転整備に向けた基本計画の策定費が計上されていると承知をしておりますが、今回国が示した新たな基準では、職員の配置や居室空間・設備設置基準に加え、運営基準として子供の権利擁護を掲げ、条例化も含めたこれまでよりももう一段階上の、一時保護中の児童がより安心して過ごせるような個別的なケアを推進する環境整備を求めています。
そこでお伺いをいたします。
一時保護所の子供の権利擁護を明確にうたった本年四月施行の内閣府令、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を踏まえ、具体的に県一時保護所の入所児童の権利擁護と環境改善にどのように取り組んでいくのかお聞かせください。
以上、明快な御答弁を期待し、壇上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◯経済産業局長(矢野剛史君)
スタートアップ・エコシステムの形成に向けた取組のうち、初めに、愛知県におけるスタートアップ・エコシステムの位置づけ及びその現状と課題認識についてお答えをいたします。
まず、スタートアップ・エコシステムの位置づけについては、本県の産業労働施策の中長期的な方向性を示したあいち経済労働ビジョン二〇二一─二〇二五において、自動車や航空宇宙産業など、あらゆる産業分野の競争力をさらに高めていく必要があり、その担い手としてスタートアップの創出、育成、誘致を図るとともに、オープンイノベーションを基本コンセプトとして、愛知独自のエコシステムの形成を目指していくとしております。
次に、エコシステムの現状については、当地域の強みである優れた人材、研究開発力、資金力を生かした世界に伍するエコシステムの形成を目指し、県に加え、中部経済連合会、名古屋大学、名古屋市、浜松市をはじめ、およそ三百の企業や団体等によりセントラル・ジャパン・スタートアップ・エコシステム・コンソーシアムを形成し、日本を代表する製造業の集積と、スタートアップとのつながりによるイノベーション創出を加速させるため、産学官金が連携した取組を実施しております。
一方で、エコシステムの形成に当たっては、起業を志す人材をさらに増やすなど、取り組むべき課題もあることから、県やSTATION Aiにおける取組をはじめとして、関係者との連携を一層密にして、愛知の産業全体の成長につながるエコシステムの強化に取り組んでまいります。
次に、プレ・ステーションAiで得られた成果と課題、STATION Aiを中核としたスタートアップ・エコシステムの形成に向けた取組についてお答えをいたします。
プレ・ステーションAiでは、コミュニティーの形成及びスタートアップの成長という二つの視点を念頭に運営を行ってまいりました。
コミュニティーの形成については、メンバー四百二十六社によるネットワークが構築され、STATION Aiのスタートアップの集積に向けてよい流れをつくることができたと考えております。
また、スタートアップの成長については、出口戦略としてのM&A、事業売却とIPO、株式上場に合わせて三社が到達したほか、多くのメンバーが起業、事業連携、資金調達に成功しております。
一方で、課題としては、プレ・ステーションAiにおいては起業間もないシード・アーリー期のスタートアップのみを対象として支援を行ってきたところですが、新たな価値を創出するオープンイノベーション推進の観点からは、スタートアップのみならず、パートナー企業も含めた多様な集積が重要であると考えております。
そのため、STATION Aiにおいては、ミドル・レイター期を含むスタートアップに加え、事業会社、金融機関、大学、支援機関等の多様な団体を誘引し、幅広く厚みのあるスタートアップ・エコシステムの形成につなげてまいります。
次に、モノづくり融合型の愛知県独自のスタートアップ・エコシステムの現状認識及び今後の取組についてお答えをいたします。
DXやGXといった世界的な潮流が高まりを見せる中、モノづくり企業は、AI、IoTなどデジタル技術を活用した生産プロセスの高度化や、カーボンニュートラルの実現に向けた環境負荷低減への対応、人手不足の解決に資するロボット等を活用した省人化の取組など、新たな課題に取り組む必要があります。
こうした中、モノづくり企業がこれらの課題に的確に対応していけるよう、本県では、製造業を中心とした県内企業と全国のスタートアップとをマッチングして企業の課題解決を目指すあいちマッチングを二〇一九年度から行っており、オープンイノベーションに対する意識の変革に取り組んでおります。
また、こうした県の取組に加え、STATION Aiでは様々な分野におけるスタートアップと事業会社とのオープンイノベーションが不断に行われることが見込まれており、これらの取組を強力に進めることで、愛知独自のスタートアップ・エコシステムの形成を目指してまいります。
最後に、STATION Aiにおけるダイバーシティーの取組についての考え方及びスタートアップの世界における女性の活躍に向けた取組についてお答えをいたします。
本県におけるスタートアップ・エコシステム形成の目的の一つは、スタートアップを起爆剤として、この地域に数多くのイノベーションが生み出される土壌を形成することであります。
そして、数多くのイノベーションを創出するためには、STATION Aiにおいてもダイバーシティーの取組を進め、異なるバックグラウンドや経験、知見を有する人々が異なるアプローチや視点を持ち寄って、互いに切磋琢磨するということが重要であると考えております。
こうした認識の下、本県では、女性スタートアップの創出を促進するため、起業を考える女性や起業間もない女性起業家向けのセミナーやワークショップを開催するなど、女性起業家の育成やビジネス拡大に重点を置いた支援プログラムを行ってまいりました。
今後も、STATION Aiにおけるダイバーシティーの取組を進め、女性起業家の裾野拡大や、多くの女性スタートアップの活躍につなげてまいります。
◯防災安全局長(冨安精君)
在宅・車中泊避難を行う被災者への支援についてお答えいたします。
熊本地震や能登半島地震におきましては、在宅、車中泊等、避難所以外の場所での避難生活を余儀なくされる被災者が多く発生をいたしました。
在宅・車中泊避難については、物資や情報の不足、狭い空間での生活による健康状態の悪化などの問題が指摘されておりまして、南海トラフ地震を想定いたしますと、本県でもそうした方たちに適切に支援が届けられるようにすることが課題になるものと認識をしております。
このため、本県では、愛知県避難所運営マニュアルに、避難所以外の場所の被災者に物資や情報を届けるための在宅避難者等支援施設の設置を検討すべきであることを示し、市町村の取組を促してまいりました。
そのような中、本年六月に内閣府が公表いたしました在宅・車中泊避難者等の支援の手引きにおきましては、こうした在宅避難者の支援拠点に係る取組に加え、車中泊避難を行うスペースを事前に検討、公表することなどの対策を位置づけております。
県といたしましては、今後、内閣府の手引を参考に、市町村の意見を聴取しながら、避難所運営マニュアルを充実するとともに、車中泊避難者支援に取り組む市町村の事例を紹介するなど、在宅・車中泊避難者等への支援の一層の充実に向けて取り組んでまいります。
次に、専門ボランティア団体の受入れについてお答えをいたします。
専門的な知識、技能を持つNPO・ボランティア関係団体等による支援は、被災者からのニーズに寄り添い、より適切、効果的な災害対応を行うために大変重要でございます。
一方、過去の災害におきましては、団体間の十分な連携が取れずに、支援の偏在や重複が生じたといった課題も指摘されております。
このため、本県では昨年度より国のモデル事業を活用いたしまして、NPO等の活動支援や活動調整を行う災害中間支援組織を含めた連携体制の構築につきまして検討を進めてまいりました。
昨年度は有識者やボランティア団体との検討会議を開催し、専門的な知識を持つNPOを把握するため、アンケートを実施いたしました。
また、今年度は六月に県地域防災計画を改定し、災害中間支援組織の育成に努めることなどを位置づけるとともに、引き続き、国のモデル事業を活用いたしまして、検討会議の開催などの取組を進めております。
今年度末には、こうした検討の成果を踏まえたシンポジウムの開催を予定しております。
県といたしましては、引き続き、災害中間支援組織の設立に向けた機運の醸成を図り、関係機関、団体等との連携体制の構築に向けて、しっかりと取り組んでまいります。
続きまして、避難所の閉鎖を見据えた取組についてお答えをいたします。
指定避難所となりました学校、公民館等におきましては、時間経過とともに施設本来の役割に戻そうとする動きが出てまいります。
このため、早い段階から避難所の今後の見通しを示すとともに、ライフラインの復旧、応急仮設住宅の建設などの時期を捉えて、避難所の閉鎖と集約を検討できる体制を準備しておくことが重要であります。
県では、愛知県避難所運営マニュアルにおきまして、発災から撤収期までの流れを示し、避難所運営の基本方針の一つとして、ライフラインが復旧する頃まで設置をし、復旧後は速やかに閉鎖することを掲げ、将来の閉鎖を織り込んだ運営の在り方を示しております。
一方、避難所を出ることができない方には、移転先が見つからない、地域のつながりを失いたくないなど、様々な理由がありますことから、市町村には、避難者の事情を聞き取りながら、きめ細やかに対応することが求められます。
そうしたことから、県では能登半島地震における避難所運営支援を通じて得られたノウハウなどを整理し、マニュアルを充実いたしますとともに、避難所運営研修を活用して市町村と共有をしてまいります。
避難所の撤収期においても避難者にしっかりと寄り添い、適切に対応できるよう、市町村の取組を支援してまいります。
◯福祉局長(加藤明君)
児童相談センター及び一時保護所職員の人材育成と連携についてお答えいたします。
経験の浅い若手職員が増える中、職員が子供と家庭を支えるための専門性、実践能力を備え、児童相談センター及び一時保護所双方が子供を中心に連携を密に図ることは大変重要であると考えております。
本県では、児童相談センターの初任者法定研修に加え、二年目職員を対象に、一時保護後の保護者面接や威圧的な保護者への対応など、様々な場面を実践的に学ぶ研修を独自に実施するとともに、一時保護所では子供の権利擁護や障害児への支援方法などをテーマとした研修を年十回程度開催し、若手職員の支援力と養育力の向上に取り組んでおります。
また、センターの新任職員が一時保護所の現場を体験する機会を設けているほか、一時保護所での生活から把握できる子供の行動特性など、常日頃から双方で情報共有し、連携しながら支援に当たっているところです。
こうした取組とともに、職員のキャリア形成において双方の職場を経験する人事配置に努めるなど、引き続き専門性の向上と連携の強化にしっかりと取り組んでまいります。
次に、一時保護所の設備及び運営基準を踏まえた取組についてお答えいたします。
この四月に施行された国の基準では、居室面積の基準や個室化の必要性に加え、入所児童の権利に十分配慮した施設運営が求められております。
従来から本県では、一時保護所の個室化を順次進めてきたところであり、また、一時保護に当たり一時保護を行う理由や子供の権利について丁寧に説明を行うとともに、一時保護中は定期的に子供の意見を聞く場を設け、余暇の過ごし方などについて、子供の声を施設運営に反映させております。
さらに、今年度からの新たな取組として、一時保護中の子供の考えや思いを周囲へ伝えることをサポートする意見表明等支援員を月二回、一時保護所へ派遣し、子供の同意を得た上で意見を関係者へ伝え、子供の権利に十分配慮した支援につなげております。
引き続き、こうした取組を通じて子供たちが安心して生活できるよう、国の基準を踏まえた環境整備に努めてまいります。
◯知事(大村秀章君)
小木曽史人議員の質問のうち、私からは、一時保護所の環境改善をはじめとした児童虐待への対応についてお答えをいたします。
一時保護という急激な環境の変化により不安を抱く子供たちの権利を守り、安全で安心できる場所を提供することは、子供の安定した生活を支える上で大変重要であります。
県では尾張地区と三河地区に一時保護所を設けておりますが、このうち三河地区の建物は、建築から五十二年が経過をしており、老朽化も進んでおりますということで、本年四月に施行された国の基準に十分適合した建物として環境改善を図るため、同じ三河地区内で移転整備、新築を行うことといたしました。
移転整備に当たりましては、近年増加傾向にあります一時保護に的確に対応するため、定員を現行の四十八名から十二名増やしまして六十名として受入れ体制の強化を図ることとし、今年度中に敷地や建築条件、建物の構造、スケジュールなどについて基本計画をまずは策定をしてまいります。
また、こうした一時保護にもつながる児童虐待への対応を強化するため、現在、児童相談所から警察に提供しております児童虐待事案に係る情報につきまして、児童相談所のシステムを今年度中に改修いたしまして、即時、リアルタイムに情報共有できる体制を構築してまいります。そのための補正予算をこの九月議会に提案をさせていただいているところでございます。
子供たちの命と笑顔を守り、全ての子供が安全・安心に暮らすことができるよう、一時保護所の環境改善とともに、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応にしっかりと取り組んでまいります。
◯二十番(小木曽史人君)
大村知事はじめ、御答弁ありがとうございました。
では、三項目それぞれについて要望をいたします。
まず、スタートアップ・エコシステムの形成についてですが、STATION Ai開業を目前に控え、まさにキーワードとなるオープンイノベーションにより新たな扉が開かれるわけで、その波及効果で国内外から新たに多くの人の流れが生まれることが期待をされます。
ただ、STATION Aiにおけるスタートアップ・エコシステム形成の中に幾ら魅力的な支援メニューを充実させても、愛知県が暮らしやすい環境でなければ人は集まらず、起業してもその定着と事業拡大にはつながりません。
それは、例えば、多文化共生意識の醸成、グローバルな人材育成を含めた教育、安全で暮らしやすいインフラ整備など、人の暮らしに関わるあらゆる県施策に通ずるところだと思います。
ぜひSTATION Aiを中核としたこれからのスタートアップ・エコシステムの形成が最大化されるよう、それを下支えする部局横断的な暮らしの環境整備も並行して進めていただきたいと要望します。
そして、何より愛知といえばスタートアップ、子供から御年配の方まで誰もが知っている耳なじみのある言葉として広がることが、まさに愛知発の、紛れもない愛知生まれのスタートアップ・エコシステムの形成と発展につながるのだと思います。
せっかく愛知県にSTATION Aiというこれから世界に羽ばたくシンボリックな拠点が整備されたのであれば、これを契機にスタートアップ・エコシステムの考え方を多世代に発信し、裾野を広げ、将来世代につなぐための取組を県としても積極的に取り組んでいただくことを要望いたします。
次に、大規模災害への備えについてです。
県地域防災計画修正案要旨の資料には、専門ボランティア団体のハブ機能として期待される災害中間支援組織について、災害時の官民連携の体制として、行政と市町村災害ボランティアセンターとの連携のポンチ絵がついております。
答弁では、国のモデル事業を活用して、災害中間支援組織の設立に向け、機運の醸成を図りつつ、取組を進めているとのことですが、今災害が起きれば、それがまさに絵に描いた餅になってしまいます。
大規模災害発災時に県が設置する広域ボランティア支援本部との役割の明確化も含め、災害中間支援組織の設立と、発災時に専門ボランティア団体がしっかり力を発揮できるような具体的な連携体制の中身を、可及的速やかにお示しいただくよう要望をいたします。
最後に、児童虐待への対応についてです。
子供を虐待から守るための肝となるケースワーク、幾らスキルアップして対応力を強化しても、児相職員に親と子供に全力で向き合う時間的余裕がなければ、必要な支援とケアは行き届きません。そういった意味では、児相職員が担っている、その他付随する業務負荷を低減することも考える必要があります。
例えば、一時保護先の空き状況については、児相職員が事案発生都度、施設等に問合せをしているといった現状に対し、今年度の県の行政課題解決に向けた実証実験を行うアイチクロステックのメニューの中に、ICTを活用した一時保護先の空き状況の見える化が上がっており、実証実験が進められるとお聞きをしております。
現場の児相職員が使いやすい、業務負荷の低減に資するものとして実装されるよう期待するとともに、児相職員の業務を棚卸ししつつ、その他業務についても効率化できそうなものがあれば、積極的に検討を進めていただくことを要望し、質問を終わります。