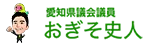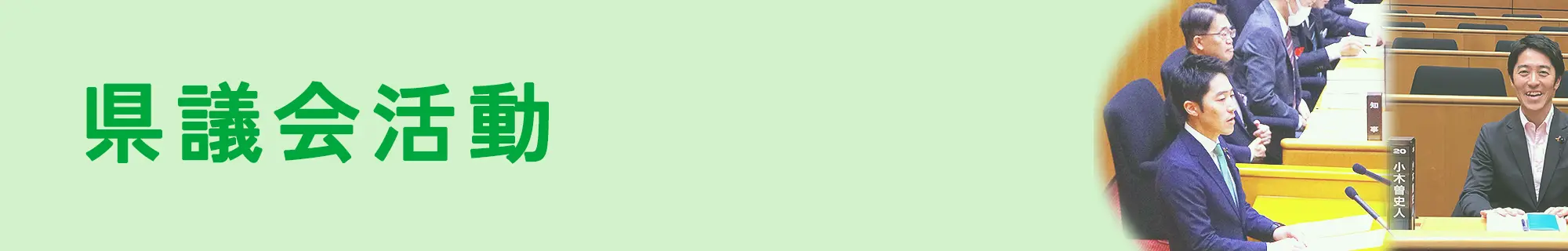

令和6年警察委員会 本文 2024-10-04
【小木曽史人委員】
大麻事犯の現状と大麻関係法令の改正に伴う対応について伺う。
愛知県における薬物事犯検挙人員は、平成8年以降連続で1,000人を超える高水準で推移している。特に覚醒剤事犯の検挙人員が多かったが、近年は減少傾向にある。一方で、大麻事犯検挙人員は年々増加しており、昨年大麻の検挙人員が過去最多の487人に上り、初めて覚醒剤の検挙人員を上回ったと聞いている。
そこで、まずは愛知県における大麻事犯の現状と取締りの状況について伺う。
【組織犯罪対策課長】
令和6年8月末現在の大麻事犯の検挙人員は、暫定値ではあるが282人と前年と同様に高水準で推移している。特に、10代、20代の若年層が約8割を占めるなど、若年層への大麻の蔓延が強く懸念される状況にある。
大麻の蔓延の背景には、インターネットやSNSの普及により大麻の入手が容易になっていることが原因の一つとして考えられる。県警察としては、薬物事犯の取締りに関して末端乱用者に対する取締りだけではなく、薬物の供給を遮断することが重要と考えており、密売組織の壊滅に向けた捜査を推進している。特に、大麻事犯については、インターネットやSNSを利用した密売事犯の取締りに力を入れて取り組んでいる。
【小木曽史人委員】
現状のいわゆる大麻事犯の検挙は、大麻の所持、譲受け、譲渡しなどが取締りの対象になっていると理解しているが、昨年12月に大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、いわゆる麻向法が改正されている。これは、大麻乱用の厳罰化で、大きく三つの内容となっている。
一つが、これは一番大きいと思うが、大麻の使用罪が新設され、罰則が強化されている。例えば、単純所持の罪の法定刑が5年以下の懲役から7年以下の懲役にされた。また、大麻由来成分を含む医薬品の使用禁止規定を削除しており、医療分野でも大麻を活用することが可能となるなどの改正法が本年の12月12日に施行されることになっている。施行日以降に大麻を使用した場合は、この麻向法違反、大麻使用罪になると思う。
この改正法施行によって今後大麻使用罪での摘発事例が多く発生することが予想されるため、捜査体制を強化しておく必要があるのではないか。捜査体制の強化は、例えば摘発に必要な捜査員の数の増強や、摘発するための捜査員の知識の習得も当然必要であると思う。もう一つは、所持や売買のように物理的な証拠が使用罪においては明確でなく、使用後に残る証拠が限られるため、尿検査や血液検査等の科学的検査を活用すると考えるが、そのための検査技術や機器の整備などのシステムの整備が考えられると思う。
そこで、12月12日からの改正法施行を控えて、取締りに必要なリソースや人員の確保について県警察としてどのように考えているのか伺う。
【組織犯罪対策課長】
県警察としては、改正法の施行に向けて迅速かつ適正に取締りが行えるよう捜査員に対する指導、教養、必要な資機材の整備等を着実に進めている。また、必要な人員の確保については、薬物情勢を含む様々な治安情勢等を踏まえながら、適切に対処していく。
【小木曽史人委員】
適切に対処するとのことであるので、犯罪が増えてくるのではないかという構えはしっかりとしてほしいと思う。
そういった中で、大麻事犯は若年層、特に10代、20代の若年層が約8割を占め、若年層への蔓延が懸念されている。愛知県内の年代別大麻取締法違反被疑者検挙人員の令和元年から令和5年の過去5年間の推移を見ると、30代、40代はほぼ横ばい。20代は増加傾向で、これが一番顕著であり、令和元年は122人だったものが昨年、令和5年は283人と2.3倍に増加している。10代も増加傾向で、令和元年には39人だったが令和5年は78人と倍増している状況である。これは、10代で初めて大麻を使用するケースが増加しており、使用した動機も興味本位やその場の雰囲気など、安易に手を出している実態があると思う。誰かが持っていて、一度吸ってみないかといって使用しているケースが非常に多く潜んでいるのではないかと思っている。
大麻は、SNS等でも依存性はほとんどないとか、健康や精神への影響が少ないといった若者の間違った認識が広がっていることや、SNSで手軽に入手できることが背景にあると思う。また、大麻はさらに刺激の強い、毒性の強い薬物に手を出す例が多く、いわゆるゲートウェイドラッグと言われており、まずは増加傾向にある10代、20代の若年層に対して時機を捉えた、県警察としても積極的な警鐘を鳴らすことが大事だと思う。
そこで、改正法施行を控えたこのタイミングで、特に若年層に向けた使用罪創出を含む大麻乱用の厳罰化についての広報、啓発の強化についてどのように考えているのか伺う。
【組織犯罪対策課長】
県警察では、これまでも関係機関と連携して街頭キャンペーンや薬物乱用防止講話を実施するなど、薬物乱用の根絶に向けた広報、啓発活動を推進している。引き続き街頭キャンペーンや薬物乱用防止講話等の機会を通じて、法改正の趣旨について県民に周知を図るとともに、SNS等の若年層の目にとどまりやすい媒体を活用した広報、啓発活動についても推進していきたいと思っている。
【小木曽史人委員】
時機を捉えることは非常に大事だと思っている。施行日である12月12日に近くなってくるとマスコミ等でも取り上げられる可能性はあるが、前もって県警察としても特に若年層に対して、先ほどSNS等いろいろな媒体を使って広報、啓発していくと答弁があったが、しっかりと進めることを強く要望する。