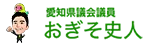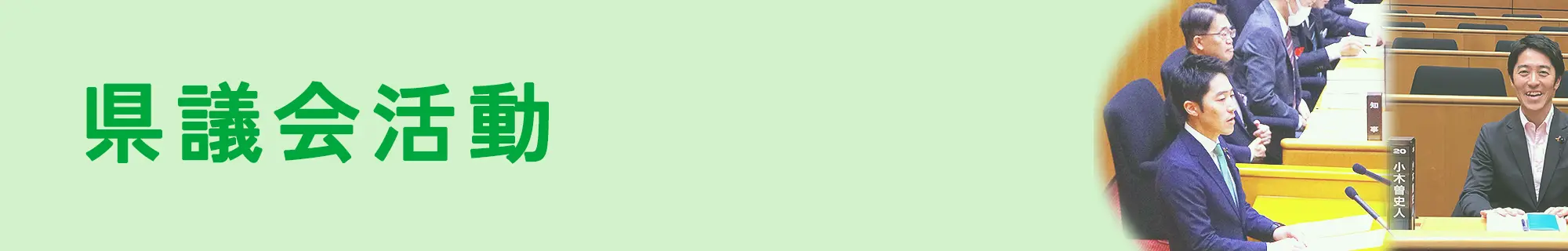

令和7年2月定例会(第6号) 本文 2025-03-05
◯二十番(小木曽史人君)
私からは、歳出第三款県民環境費第三項社会活動推進費のうち、外国人県民に対する施策を軸に、大きく二点、順次お伺いをしていきたいと思います。
まず一点目、外国人県民に対する日本語教育推進の取組についてです。
本県には、製造業を中心として多くの外国人労働者が流入し、活躍をしております。
また、昨今の労働人材不足から、国は特定技能制度の対象職種の拡大や、技能実習制度を廃止、育成就労制度への移行など、在留資格制度を改正し、積極的に外国人労働者を受け入れる体制を整備しています。
ただ、世界的に見れば、外国人労働市場も変化しており、外国人材について、県としても流入という受け身の視点ではなく、言わば積極的に受け入れる姿勢を示し、愛知県が選ばれる場所を目指す必要があります。
そのためには、企業による働きやすい環境整備もさることながら、共に地域で暮らす仲間として共生していける安心、快適な生活環境の整備が求められることは言うまでもありません。
この共生とは、まさに外国人が平時に暮らす地域社会の中で共に尊厳を守り、分かり合うことで、孤立せず、日本人と同様に生活できる、そして、有事の際、例えば災害時や医療が必要になった場合でも、困らず対応できることだと理解をしております。
その共生社会の実現の大きな課題の一つが言葉の壁です。このことは、令和三年度県民意識調査の結果、そして、昨年度、国が実施した在留外国人に対する基礎調査結果からも明らかであり、コミュニケーションツールとしての日本語教育の充実のため、本県でも様々な角度から市町村や各種団体と連携した支援施策を実施していると承知をしております。
学校や地域で様々な主体による外国人県民への日本語教育支援が実施されていますが、国籍、在日歴、年齢に加え、習熟度も様々なことから、その教育現場は大変苦慮されており、そもそも、日本語を学びたいと望む外国人県民のニーズに応えるための担い手不足の現状は依然として厳しいという声をよく耳にします。
そこで、まず、地域日本語教室の担い手不足の課題に対し、県としてどのように認識しているのか、また、担い手不足の解消に向けてどのように取組を進めていくのか、お伺いをいたします。
地域の日本語教室では、現状、それぞれの担い手が手探りの工夫を凝らしながら、独自のテキストや進め方で指導していることから、教室ごとのレベル感はかなり差があるという声も伺っております。
担い手不足の中、多様な主体に対し、レベルに応じ効率的かつ効果的な日本語教育を地域で広く普及、充実させるためには、担い手が取り組みやすい素材や仕組みをツールとして提示することが重要であり、第四次あいち多文化共生推進プランでは、そのツールとして人材育成カリキュラムの開発を掲げています。
これは地域の日本語教室における指導者のための教科書的なもので、教材の使い方や対話型の日本語指導の進め方をまとめたものだとお聞きをしております。今回、当初予算の中にはこの人材育成カリキュラムの開発費が計上されており、県内の地域日本語教育の底上げにつながると大いに期待したいと思います。
そこで、この令和四年度から開発を進めてきた人材育成カリキュラムをいよいよ来年度作成することとしていますが、どういったカリキュラムを想定しているのか。また、カリキュラムの具体的な展開及び使用方法など、実効的な現場での活用方法をどのように想定しているのか、お伺いをいたします。
人材育成カリキュラムの作成は、指導者の育成、地域の日本語教育拡充の大きな一歩ですが、あくまで目的は、そのカリキュラムに沿った教育を受けた外国人県民の習熟度を効率的かつ効果的にアップさせることです。
第四次あいち多文化共生推進プランでは、本県独自の日本語能力判定ツールの開発を行う方針を掲げていると承知をしており、一昨年の一般質問でも早急な開発着手を要望したところであります。
この判定ツールがあれば、外国人県民が日本語を学びたい、地域の日本語教室に参加したいと希望した際に、ほとんど日本語が話せない学習者を市町村が運営する初期日本語教室に案内をしたり、地域の日本語教室のクラス編成や指導者の人数に反映し、その習得レベルやニーズに合った段階的な日本語教育支援を行うことができると考えます。
そこで、日本語の習得レベルやニーズに合った支援を行うことができる日本語能力判定ツールの開発の進捗についてお伺いをいたします。
続いて、二点目、外国人県民の地域における活躍支援の取組についてです。
この件についても一昨年の一般質問において、南米調査での日系人の活躍に絡み、外国にルーツのある方が地域の中で多文化共生の取組にどう関わり、活躍しているのか、また、その活躍支援についてお伺いをしたところでございます。
愛知県地域日本語教育の推進に関する基本的な方針の中では、外国人県民の役割として、他の外国人県民の日本語学習を支援する側に立ち、外国人県民と日本人県民の相互理解を促進すると示されています。
多くの外国人県民の方は、母国のつながり、地域のつながりで、SNS等を活用しながら、外国人コミュニティーを形成しております。その中には、長年日本で暮らし、日本の文化、慣習に慣れ親しみ、地域社会とうまくつながり生活している外国人県民の方も大勢いらっしゃいます。
日本語も母語もある程度話すことができ、リーダー的な存在としてコミュニティーをまとめていらっしゃるような方であれば、日本人と外国人県民の相互理解を深めるかけ橋的存在として活躍していただきたいですし、ぜひ活躍したいと考えていらっしゃる方もいると思います。
実際、本年一月、地元のとある行事で、長年地元に住み、日本語も達者で、十分にそのキーパーソンとなり得るような外国人県民の方お二人とお会いをし、お話をする機会を得ました。
その際、地域の外国人コミュニティーをまとめ、その中で地域社会と共生するためにできることは積極的に参画していきたいが、必要な情報のやり取り等を行うための窓口など、どことどのようにつながり、参画していってよいか、具体的に分からないとおっしゃっていました。
そういった方には、行政としても日常的なつながりを持ちつつ、地域での日本語学習支援をはじめ、もっと活躍できる場を積極的に提供し、その活動を後押しすべきですし、中でも、特に有事の際、南海トラフ地震等大規模災害時に外国人支援活動のキーパーソンとして大きな役割を担っていただくことが期待をされます。
そして、来年度、多文化防災推進事業として、市町村の災害時外国人支援体制や防災教育等の実施状況等を調査するとともに、地域の外国人キーパーソン等にヒアリングを行うとしています。
そこで、今回、地域の外国人キーパーソンへのヒアリングを新規に予算化した課題認識を含む背景についてをお聞かせください。
あわせて、ヒアリングを行うには、その前提としてそのキーパーソンをまず把握することが必要ですが、どのようにキーパーソンを把握し、今後、そのキーパーソンが実際に地域で活躍するために、その活動を後押しする主体としてどこを想定し、そのキーパーソンに具体的にどのように活躍してほしいのか、そのスキームと考え方についてお伺いをいたします。
◯県民文化局長(森岡士郎君)
外国人県民に対する日本語教育推進の取組についてのお尋ねのうち、まず、地域日本語教室の担い手不足に対する認識と解消に向けた取組についてお答えします。
県内にはボランティア等が中心となって運営する地域日本語教室が二百以上あり、教室関係者からは担い手が不足して困っているとの声を多く聞いております。
地域の日本語教室は、外国人県民の日本語学習を支援するだけではなく、教室参加者の居場所として、あるいは、地域との相互理解を図る場としても重要な役割を果たしており、本県としましては、教室の運営を担う一定の専門知識を持った人材の育成は重要な課題であると認識しています。
本県では、二〇一八年度から市町村が主体となった日本語教室の普及に取り組んでおり、教室の立ち上げ支援を目的としたモデル事業や、教室活動の企画、運営を担う指導者の養成講座、その修了者を対象としたフォローアップ講座を毎年継続して開催しております。
こうした取組により、これまでに約二百名の指導者を養成しており、地域の日本語教室で御活躍をいただいております。
今後も、こうした取組を県が主体となって継続して実施することで、地域日本語教室の担い手不足の解消に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、日本語教室の指導者養成で活用する人材育成カリキュラムについてお答えいたします。
本県が推進する地域日本語教育に必要な日本語での対話を中心とした指導力や、行政や地域社会との調整役を担う人材を養成するため、二〇二二年度から独自の人材育成カリキュラムの開発を進めております。
具体的には、二〇二三年度は、教室の企画、運営を担う指導者を養成するためのカリキュラム案を作成し、今年度は、行政などの多様な機関との連携、協力を担うコーディネーターの役割と育成の方向性を示したモデル案を作成しているところであります。
さらに、来年度は、二〇二三年度に作成した指導者養成のカリキュラム案を基に、ワークシートの活用方法などの教室運営の質を高める技術や、県や市町村が行う多文化共生施策に関する知識を習得できるカリキュラムへとアップデートしてまいります。
こうしたカリキュラムは、県の養成講座で活用するだけではなく、市町村やNPO等が運営する地域日本語教室においても活用していただけるよう、県ウェブページのあいち多文化共生ネットに掲載するとともに、具体的な活用方法を学んでいただく講座を県主催で開催することで、人材育成カリキュラムの実効性を高めてまいりたいと考えております。
次に、日本語能力判定ツールの開発の進捗についてお答えします。
議員お示しのとおり、地域日本語教室において効果的な指導を行うためには、学習者それぞれの日本語能力の習得レベルを適切に把握することが重要となります。
国においては、既に二〇二二年九月に日本語能力自己評価ツールを作成しておりますが、このツールは外国人自身が簡易に日本語能力の習得レベルを確認することを目的としており、地域の日本語教室において客観的かつ適切にレベルの判定ができるツールとはなっておりません。
また、本県が実施している地域日本語教育モデル事業やオンライン日本語教室においても、参加者の日本語レベルの判定は事業の受託事業者ごとに独自の基準で行っているのが現状であり、学習内容に合わせた適切なレベル分けができていないことが課題となっております。
このため、本県においては、日本語教育の専門家として多文化共生推進室に配置している二名の総括コーディネーターが中心となって、類似のツールの調査研究や、本県が作成する独自の能力判定ツールの方向性の検討を行っているところであります。
現時点での進捗状況につきましては、県としましては、まずは人材育成カリキュラムの開発が優先課題と考えており、日本語能力判定ツールの開発については、第四次あいち多文化共生推進プランの計画期間である二〇二七年度までのできるだけ早い時期の完成を目指して、取り組んでまいりたいと考えております。
次に、外国人県民の地域での活躍支援の取組についてのお尋ねのうち、地域の外国人キーパーソンへのヒアリングを予算化した課題認識、背景についてお答えいたします。
大規模災害発生時に日本語が分からない外国人県民の皆様が安全に避難し、必要な支援を受けるためには、行政が正確な災害情報を多言語で発信するとともに、避難所等において外国人の避難状況やニーズを正確に把握し、支援活動を行う行政やNPO等と、その情報を迅速に共有することが重要となります。
こうした取組を行う上で、外国人コミュニティーにおいて母語で日常的に情報を発信したり、リーダーとして活躍している外国人キーパーソンの役割は極めて大きく、そうした方々と行政が日頃からいかに緊密な関係を構築しておくかが課題であると認識しております。
こうしたことから、来年度は、地域で活動する外国人キーパーソンの方々を幅広く把握し、災害時に外国人コミュニティーが必要とする情報や、キーパーソンの方に活動していただく上での課題などについてヒアリングを行うとともに、災害時の外国人支援体制を検討する会議の委員としても参画していただくことで、各市町村と外国人キーパーソンの方々が平時から連携を深めていくための具体的な取組を検討してまいります。
最後に、外国人キーパーソンの把握方法、期待する活躍内容等についてお答えいたします。
どの地域にどのような外国人キーパーソンが在住しているかを把握するため、現在、市町村に対して、災害時に行政と連携して活動いただくことが可能な外国人キーパーソンについての調査を依頼しております。
しかしながら、市町村においても、全ての外国人キーパーソンを把握することは容易ではないと考えられることから、市町村が現在把握している外国人キーパーソンの協力を得て、それぞれの方の持つネットワークを情報源にして、さらなる発掘をしてまいりたいと考えております。
平時からできるだけ多くの方とのつながりを持っておくことによって、災害発生時には、外国人キーパーソンが持つ外国人の被災状況に関する情報や、避難所における現場のニーズなどを、行政やNPO等の支援者と外国人被災者の双方に正確に伝える役割を担っていただきたいと考えております。
さらには、外国人コミュニティーにおける支援活動のリーダー役を担っていただくことで、多くの外国人県民の方々が支援する側として活躍していただくことも期待しております。
こうした外国人キーパーソンの活躍を後押しする主体は市町村が中心となりますが、本県としても、防災訓練や会議などへの参加を積極的に働きかけるとともに、災害多言語支援センターの機能強化にも御協力をいただくことで、多様な主体が連携した災害時の支援体制の構築にしっかりと取り組んでまいります。
◯二十番(小木曽史人君)
御答弁ありがとうございました。
それでは要望いたします。
答弁にもありましたが、第四次あいち多文化共生推進プランの計画年度は二〇二七年度までです。人材育成カリキュラム、当然、つくって終わりではなく、作成後、指導者養成講座や、市町村、NPO等、地域で実施されている日本語教室で広く活用をしてもらって効果検証し、次のプランにつなげるサイクルを回さなければなりません。
あわせて、効果検証には、このカリキュラムに基づく指導により指導を受ける外国人県民の日本語能力がアップしているかを段階に応じて見えるようにする日本語判定ツールが両輪で必要だというふうに考えます。学校教育現場でも、先生がテキストに基づいて授業を実施し、定期テストや単元テストによって児童生徒の習熟度を確認しながら、段階的な教育を実施していることと同じことです。
この判定ツールを一から練ってつくり上げるにはそれ相応のリソースが必要ですが、例えば、豊田市では独自の判定ツールを用いているとお聞きしており、参考にできる事例もあると思うので、まずは県独自のプロトタイプを作成し、トライアルとして地域の初期日本語教室でモデル的に実施してみることもできると思います。
来年度は現行プランの中間年度、ぜひ速やかなカリキュラムの作成と、担い手への分かりやすい、使いやすい落とし込み、そして、並行して、日本語判定ツールの早期開発と実装を重ねて要望し、質問を終わります。