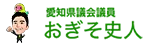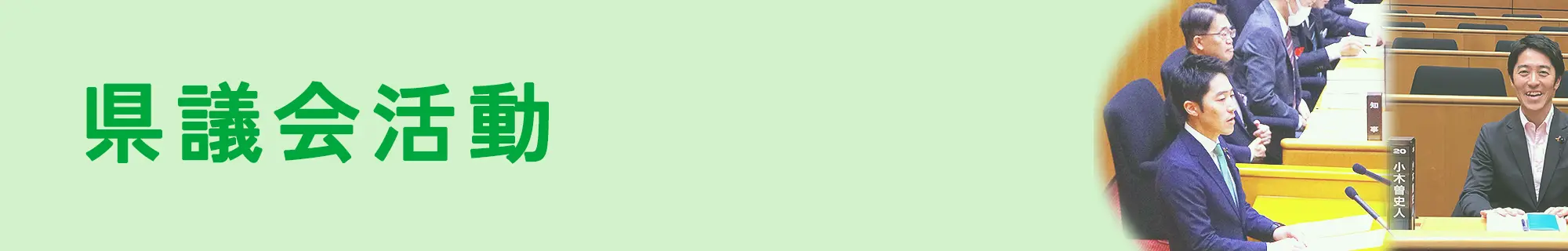

令和7年6月定例会(第4号) 本文 2025-06-25
◯二十番(小木曽史人君)
通告に従い、私からは大きく四項目について順次質問をいたします。
まず初めに、Aichi─Startup戦略についてです。
本県においては、成長戦略の起爆剤として期待されるスタートアップ・エコシステムの形成に向け策定されたAichi─Startup戦略を改定しつつ、変化の激しい世界的なイノベーション環境に対応するための新たな取組を適宜進めていると承知をしております。
全国的にも各都道府県や地域が産官学金連携した独自のスタートアップ・エコシステム形成計画を策定しており、都度、多面的評価できる成長度合いを見極めるための独自の定性的・定量的目標、いわゆるKPIを設定しております。
Aichi─Startup戦略におけるKPIは、令和二年七月に内閣府に選定された愛知・名古屋、浜松地域で構成するセントラル・ジャパン・スタートアップ・エコシステム・コンソーシアムのスタートアップ・エコシステム拠点形成計画の目標と共通しています。
この第一期の計画では、二〇二〇年度から二〇二九年度までの十年間でユニコーン企業の創出を五社以上としているほかは、昨年度までの五年間で、イノベーション人材の輩出一万人以上、新規事業開発件数千件以上、海外スタートアップと当地域企業とのビジネスマッチング件数四百件以上、資金調達額一千億円以上、スタートアップの起業数県内二百社以上、中部圏三百社以上、百億円以上の売上げ規模のスタートアップ創出十社以上と設定をされております。
そして今月、内閣府によりセントラル・ジャパン・スタートアップ・エコシステム・コンソーシアムが第二期スタートアップ・エコシステム拠点都市の広域都市圏型に選定、世界各国との広域ネットワークを生かした多様なスタートアップ支援、STATION Aiをはじめとするオープンイノベーション拠点における機運醸成や事業創出、東海地域の二十七大学、研究機関と連携したアントレプレナーシップ教育などを進めることとし、二〇二九年度末までの新たなKPIが示されたところです。
そこで、第一期グローバル拠点都市のKPIの評価と分析、第二期グローバル拠点都市のKPIの考え方についてお伺いをいたします。
こうした中、スタートアップ支援拠点であるSTATION Aiに大きな役割が今後ますます期待されるところです。昨年十月のオープン以来、入居スタートアップ、パートナー企業、団体数も増加、モノづくり企業も多く入居しており、コワーキングスペースはまだ余裕があるものの、個室、固定席はほぼ満席とのこと。STATION Aiのパートナー企業とスタートアップの入居の在り方、バランスなど今後検討されていくと思いますが、機能を最大化するためには何よりもまずオープンイノベーションへの期待感を醸成しなければなりません。
入居企業、団体が企画提案するリバースピッチでは、二十件を超えるマッチング成果があったと伺っていますが、まだまだ圏域の優位性を生かしたオープンイノベーションへのマインドチェンジが十分とは言えず、ポテンシャルを引き出すモノづくり融合型の具体的なビジネスモデルを創出するための新たな流れを生み出す必要があります。
そこで、KPI達成に向け、役割が大きく期待されるSTATION Aiにおいて、今後のオープンイノベーションを進める取組についてお伺いします。
また、第二期に示されたKPI達成には、スタートアップのマインドセットを県下全域に広めていくことも重要です。
県下自治体や団体のスタートアップのマインドセットを誘引する取組として、県は令和四年度からアイチ コ・クリエーション スタートアップ プログラムを開始し、参加自治体及び団体数は着実に増加していると伺ってもいます。
自治体が抱える課題解決とスタートアップは親和性が高く、既に幾つかの自治体がプログラムのピッチイベントなどを通じて実証事業等を実施していると聞いており、今後さらにスタートアップとのマッチングを通じた様々な市町村事業の展開が期待されますが、マインドの醸成にばらつきがあり、海部津島地域を中心にまだまだ市町村の意識が高まっている状況になっていません。具体的なマッチング事業の内容、成果を含めた取組を積極的に公表するなど、参加していない自治体にも参加を促す取組を加速していただきたいと思います。
そこで、アイチ コ・クリエーション スタートアップ プログラムのこれまでの取組と、さらなる自治体等の誘引やマッチングを進めるため、県としてどのように取り組んでいくのか、お伺いをします。
次に、学校内で発生している事案等を踏まえた危機管理対応について伺っていきます。
本年五月八日、東京都立川市の小学校で侵入した男二人が暴れて教職員がけがをしたという事件が発生。本県でも、ある県立高校では、本年四月以降、校内にて生徒の金銭が盗まれる事件が四件発生、五月には、平日の通常授業中にもかかわらず、校舎内にいる不審者を巡回中の教職員が目撃、逃走する事件が発生したとのこと。この事案について県教育委員会は把握しておらず、これは私の地元の保護者からお聞きした情報で、もしその者が刃物を持った錯乱者だったらと思うと恐ろしいとおっしゃっており、私も本来安全・安心な場所であるはずの学校がと改めて驚きと不安を覚えました。
愛知県では、あいちの学校安全マニュアルに基づき、全ての学校で危機管理マニュアルを作成、併せて不審者侵入事案発生時の対応訓練や研修等を実施していると承知をしておりますが、果たして実効的な危機管理がなされているのでしょうか。
文科省は令和五年度に学校の安全に係る取組状況調査を実施、不審者侵入防止対策として、校門、校門から校舎への入り口、校舎の入り口の三エリアにおける具体的な対策の記載があるかどうかのいわゆる危機管理マニュアルへの三段階チェック体制の記載やその他防犯カメラの設置などのハード対策の有無が公表をされました。
愛知県の県立高校の状況としては、詳細は割愛しますが、例えば三段階チェックの記載は小中学校が約七三%に対し県立高校は約三〇%、防犯カメラの設置は小中学校が約八二%に対し県立高校は約二一%、玄関のインターホンの設置は小中学校七五%に対し県立高校は約四%とかなり低い割合となっており、特に防犯カメラの設置等ハード整備については全国の高校、そして県内私立高校と比べても軒並みかなりの低水準になっております。
一昨年九月定例議会における藤原議員の一般質問では、三段階チェックの防犯対策の記載は全百四十九校中四十四校にとどまり、危機管理マニュアルにエリア別の防犯対策が記載されていない学校に対しては、マニュアルの修正例を示し、早急に修正をするよう指示をした。今後、各学校の危機管理マニュアルが実効性のある形で修正をされ、それが適切に運用されているのか確認していくと教育長が答弁されております。
また、さきの調査結果でも、県立高校における不審者侵入に対するハード整備の脆弱性は明らかで、来年度以降、私学無償化が実現される可能性があり、ただでさえ私立高校と県立高校の教育環境整備の差が指摘され、県立高校離れが懸念される中、安全・安心な教育環境の根本部分でいまだこうした状況にあることには早急に対応していく必要があると考えます。
そこで、県立高校において、前回の調査以降、ソフト対策としての三段階チェックの修正状況及び危機管理マニュアルが実効性あるものとして適切に運用されているかの確認を具体的にどのように行ってきたのか、併せて、防犯カメラの設置等危機管理としてのハード対策の脆弱性に対する県教育委員会の認識と今後の対応についてお伺いをいたします。
続いて内部犯行、教職員による学校内での犯罪行為への対応について伺います。
今年二月、私の地元あま市の小学校で教職員──その後、懲戒免職処分になりました。以下A氏と言います──による女子児童の更衣場所となっている教室内に動画撮影状態にしたスマートフォンを設置したという盗撮事件が発生をしました。同様の事件が、その約一か月前に千葉県市川市の小学校でも発生。事件発覚後、学校の聞き取り調査で盗撮を否定した当該教職員は帰宅後命を絶ったということです。
実は、このあま市の事件について、私は事件発生直後に、そのスマホを発見した女子児童の保護者から、学校側の初動対応に対する御相談を受けました。
ここで教育委員会にお尋ねしたいのは、具体的な教職員による犯罪行為が発覚した際、学校側としてどのような対応をするべきなのか、また、報告や相談を受ける市町村教委がどのような指示、指導をするべきなのかということです。
本県では、着替えにも使う教室で女子児童が穴の空いた箱の中に動画撮影状態のスマホを発見。たまたま相談した相手がそのスマホを設置したA氏であり、A氏はその場で動画を削除。A氏は事件発覚直後の学校側管理職の聞き取りで、指導目的の撮影として盗撮目的を否定。学校側もそれを信じ、スマホを返却。夕刻の学年集会で教頭とA氏が児童に謝罪し、A氏はそのまま当日の職務を終え退勤。その後A氏は失踪。A氏の保護者が警察へ連絡。事情の聞き取りの中で学校での盗撮疑惑があったことを警察が知り、学校側へ連絡したと聞いています。つまり、学校側から積極的な警察への通報、捜査依頼はなかったということです。
本来ならば、自己所有スマホを教室内にひそかに設置する行為自体が迷惑防止条例違反に当たり、動画撮影の事実とその態様から盗撮という犯罪行為の可能性も十分考えられるため、学校側としては即座に警察への通報義務があったとも思います。
学校という安全・安心が担保される空間での、しかも信頼されるべき教職員による盗撮は、児童生徒の心に深い傷を負わせるだけでなく、撮影動画が拡散されるおそれなどの将来にわたる不安を背負わせる極めて悪質で危険な犯罪行為です。
もちろん、学校による聞き取り調査等の事実確認を否定するものではありません。
ただ、学校側に犯罪行為の有無を捜査し、判断する権限はなく、初動を間違えれば、盗撮した教職員が学校側の聞き取りをうまくかわし、そのまま何もなかったかのように教壇に立ち続けるという、まさに児童生徒や保護者にとっては危機的状況が続く可能性があることを重大に捉えるべきです。ややもすればさきに挙げた千葉県市川市のように、当該元教職員の命までも危険にさらすことにもなりかねません。
そこで、あま市の事件のように、小中学校内における教職員による盗撮などの犯罪行為が疑われる事案が発生した際に、学校及び服務監督権者である市町村教委の初動対応について、県教育委員会としての見解を伺います。あわせて、あま市の事件を教訓とした今後の対応についてもお聞かせください。
次に、安心して子供を産み育てられる環境整備について伺っていきます。
二〇二四年の出生数、統計開始以来初の七十万人割れ、合計特殊出生率は一・一五で、前年の一・二〇を下回るという衝撃的な数値が発表されました。
一方、昨年九月のこども家庭庁の調べでは、心中以外の乳児虐待死五十六人のうち、ゼロ歳での死亡が二十五人、そのうちゼロか月児が十五人と小さな大切な命が失われたとのこと。また、ある統計では産後鬱にかかる女性が二十から三〇%に上るとも言われ、事実、四月には埼玉県戸田市で生後四か月の赤ちゃんを母親が自宅の浴槽に沈めて殺害、産後鬱が原因との報道もありました。
例えば貧困状態や予期せぬ妊娠、心身に深い問題を抱えているなど様々な複合的問題を抱えた妊婦で、出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦は特定妊婦と法的に位置づけられ、その登録者数はここ十年で約八倍、全国で約八千人以上に上るとも言われ、保健師等による支援対象になっております。
ただ、実際には自宅出産、妊婦健診未受診の飛び込み出産など母子の命が危険にさらされるケースが後を絶たず、いわゆる支援対象となっていない、行政が把握できていない悩める妊婦が多く潜在していると言われております。
そんな中、昨年四月施行の改正児童福祉法では、困難を抱える妊産婦等に対し、寄り添いや心理的ケア、出産支援、産後の生活支援などの包括的な支援事業が制度として位置づけられました。
生まれてくる、生まれてきた大切な命を守り抜くことも大切な少子化対策であり、愛知県は日本一子育てしやすく、全ての子供、若者が輝くあいちの実現をうたい、愛知県こども計画はぐみんプラン二〇二九では、妊産婦等への支援の充実が盛り込まれていると承知をしております。
ポイントは二つあると考えます。一つは特定妊婦またはその予備軍である悩める妊婦のキャッチアップ、二つ目はそうした妊婦を必要な支援に確実につなげられているのか、シームレスな支援の仕組みです。
愛知県は、キャッチアップの入り口として、女性全般の相談を受け付ける女性の悩みごと電話相談、女性の健康相談を設置、主に妊娠相談としてあいち性と妊娠相談ほっとラインというLINE相談窓口を設置しています。
ただ、妊娠に特化した相談窓口としては、現在、助産師メンバー中心のNPO法人がにんしんSOS愛知を立ち上げ、相談事業のほか、同行支援や担い手研修など幅広くサポートする事業を展開していますが、自力で事業を実施しているため、資金繰りやマンパワー不足など事業継続が厳しいといった声も伺っています。
悩める妊婦を広くキャッチアップする姿勢はもちろん重要ですが、そもそも対象者が妊娠に特化されていない、電話及びメールとLINEで事業主体もばらばらな状態で、果たして県として困難な事情を抱える妊婦の実態を把握できているのでしょうか。
そこで、まず困難な事情を抱える妊婦がどれほどいらっしゃるのか、現状と県の認識について伺います。
特定妊婦など困難な事情を抱える妊産婦をキャッチアップした後の支援も重要で、現状、産前産後の居場所の確保や自立支援サポートとして、女性相談支援センターや県、市の福祉事務所等が連携し、女性自立支援施設や母子生活支援施設等と協力して対応していると承知をしております。
ただ、女性自立支援施設は妊婦に特化した支援ではなく、幅広いDVや生活困窮で悩む女性を対象としており、基本子供が生まれたら母子生活支援施設に移ったり、一方、母子生活支援施設はあくまで出産後の一時的な入所施設の位置づけであり、妊娠期からのシームレスな支援の立てつけになっていません。
国が事業化した妊産婦等生活援助事業は、複合的な問題を抱える妊産婦に特化した事業で、看護師や専門支援員等の配置を手厚くし、出産前後でシームレスに自立支援につなげる事業とお聞きをしております。
そこで、特定妊婦等さらなる自立支援が必要な妊産婦のために、妊産婦等生活援助事業を県として事業化するといったシームレスな支援体制整備について、県としてどのように考えているのかお聞かせください。
次に、出産後の不安や悩みに寄り添う産後ケア事業について伺います。
産後ケア事業とは、母子関係の構築のスタートに伴走支援する事業で、実施主体は市町村、態様は宿泊型、デイサービス型、訪問型の三種類、事業内容は、レスパイトケアとしての母体の身体的ケアだけでなく、授乳・搾乳指導やカウンセリング、栄養管理などの生活指導、沐浴、おむつ替え、だっこ方法などの育児指導など専門的かつ多岐にわたります。
実際、利用者さんからお話を伺うと、育児指導を専門的な立場から面着で的確に教えてくれるので自宅での実践もしやすい、何より不安が解消されてとても助かった。一方で、よい事業なのに知らない人が多い、申請手続が煩雑でタイムリーに利用しづらいなどの声も。また、担い手の助産師さんからは、自治体ごとでサービス内容や助成金、対象条件がばらばら、事業経営が大変厳しい、担い手の指導スキルがまだまだ不十分などの声も伺いました。
産後ケア事業は、二〇二三年度には利用者を限定しないユニバーサルな事業となり、今年度から地域子ども・子育て支援事業に位置づけられました。なお、都道府県が実施主体となる妊娠・出産包括支援推進事業では、産後ケア事業等の実態調査と事業に当たる専門職への研修の実施のほか、市町村の体制整備を支援するとされています。
県下の状況としては、二〇二四年度には五十四市町村全てで実施、利用者数も増加傾向にはあり、ニーズの高まりがうかがえるものの、利用率は数%で決して高くありませんが、今年度から都道府県負担が導入され、当初予算でも九千万円が計上されており、サービスの充実と広がりが期待をされます。
産後ケア事業の実施に当たり、昨年十月に国から示されたガイドラインでは、県の役割として委託契約を調整するなど、市町村を広域支援することが明記されています。
その一つの手法として、県による集合契約があります。
県による集合契約とは、県が代表して、市町村の代わりに複数の病院や助産院などの医療機関とまとめて契約を結ぶ。市町村は県が契約した施設を利用し、産後ケア事業を実施できるという仕組みです。
市町村によりばらばらな利用期間やケア内容、契約金額を国のガイドラインに沿った形で統一し、手続も標準化、簡素化することで、市町村にとっては医療機関等と個別契約をするのに比べて負担軽減にもつながり、利用者にとっても、国のガイドラインに沿った安心でタイムリーなサービスを受けられ、もし住所地外の県内市町村に里帰りした場合でも近くの施設でサービスが受けられるメリットもあるように思います。
市町村並びに医療機関側の理解と調整には乗り越えるべき課題はあると思いますが、利用者目線で、事業を必要とする子育てママに広く利用してもらう仕組みとして愛知県での導入も検討に値すると考えます。
そこで、先ほど申し上げたように国の施策の中で、産後ケア事業等の実態調査、事業に当たる専門職への研修の実施のほか、市町村の広域支援を含めた体制整備支援を実施するとされていますが、県の課題認識と集合契約の導入を含めた今後の取組についてお聞かせください。
最後に、大規模災害を想定したDXの推進について、情報収集と共有の観点から質問します。
まず、大規模災害時のドローン利活用についてです。
昨年末、新城市で実施された医薬品等を山間部に届ける物流ドローンの実証実験を視察、物流と災害対応等の社会課題を起点に、ドローンの進歩と技術革新について認識を新たにしたところです。
また、あいちモビリティイノベーションプロジェクトチームの中核であるプロドローン社の戸谷俊介社長からもお話を伺い、海中の機雷やウクライナ紛争での地雷撤去など新たなドローン利活用の現状、能登半島豪雨において自衛隊からの要請でドローンによる被害状況確認を実施したことなど、現在進行形の活用事例と実装及び事業化への課題感、何より愛知県を拠点としたサプライチェーンを含めたメード・イン・ジャパンにこだわる熱い思いをお聞かせいただきました。
災害時のドローン活用としては、主に被災地の状況確認、人命救助や捜索活動、孤立集落への物資輸送、通信支援、火災や土砂崩れの監視支援など、災害時の目となり手となる大きな役割が期待できる一方、乗り越えるべき課題も幾つかあります。
天候に左右されない、バッテリーの小型軽量化、操縦者の育成、通信インフラの整備等の課題もさることながら、特に大規模災害時には、いかに安全かつ効果的に飛ばすことができるか、運用面でのルール化が課題であり、その一つが航空制御の在り方です。
大規模災害時には、自衛隊、警察、消防、県、市町村、協定を結んだ民間事業者など多くの関係機関が空を使うことが想定されます。
実際に自治体や関係機関へのヒアリング調査でも、有人航空機とドローンの航空運用の調整のルールが整備されていない、県や被災市町村とドローン事業者との協定がなく、現地入りした際に迅速な対応ができなかったなどの声があったとお聞きをしております。
そんな中、あいちモビリティイノベーションプロジェクトでは、ドローンの平時の事業化に軸足を置きつつ、災害時のドローン利活用の検討のほか、ドローンと有人航空機の間での航空運用に関する情報収集、共有といった連携の仕組みの構築を進めていると承知をしております。
そこでまず、災害時のドローン利活用に向けて、あいちモビリティイノベーションプロジェクトの中でどのように取り組んでいくのかお伺いをします。
また、大規模災害時において、関係機関から的確に情報収集し、共有できる航空運用調整の仕組みづくりについて、今後どのように取り組んでいくのかお聞かせください。
二つ目は、大規模災害発生時の被災者情報の収集、共有についてです。
能登半島地震のケースを少し御紹介します。
石川県では、発災前に県主導で県下全市町村に被災者支援システムを導入していました。しかし、導入システムの管理・運用方法が統一していなかったため、発災後それぞれの部署で支援業務が走り出し、データ作成もおのおのの判断で進められ、情報が散在し、導入されたシステムに一元化するのに手間がかかったとのこと。
最終的には、混乱の中ルール化を進め、被災者支援システムは、罹災証明の発行、生活再建支援金、家屋の応急修理、仮設住宅供与、義援金、税の減免、公費解体など被災者支援二十六業務で利用され、円滑、迅速な支援につなげたと伺っていますが、あらかじめ必要なデータ様式の整理、データ連携の仕組みづくりに加え、被災者の日常業務で使う個人情報との連携も視野に入れつつ、統一的なルールを事前に決めておく必要があったなど多くの課題が浮き彫りになりました。
大規模災害時、被災者は市町村ひいては県域を越えて避難します。いわゆる広域避難です。被災者支援制度の多くは被災時の居住市町村に申請して受けられるため、市町村単位では広域避難者に行政の支援が届きにくくなります。被災者が地域で孤立し、行政の手が届かなくなることで災害関連死のリスクは高まります。
災害関連死ゼロ、場所への支援から人への支援、広域避難の考え方を踏まえたとき、市町村が導入する被災者支援システムと県が網羅的に構築するデータベースとの連携、連動を事前にシミュレーションした上で、スムーズな被災者支援につなげる身構えをしておく必要があります。
国は市町村の被災者支援システム導入に対して財政支援をしており、本県では本年度中に二十九市町村で導入予定とお聞きをしています。
しかしながら、私の住む海部津島地域は海抜ゼロメートル以下の災害脆弱地。南海トラフ地震では甚大な被害が予想されており、広域避難については、西尾張地域十四市町村の避難元市町村と避難先市町村のマッチングが具体的に進んでいるにもかかわらず、情報連携、共有の肝となるシステムが導入されているのは大治町のみです。
先月、災害対策基本法の一部改正案概要の事業メニューの中で、避難元、避難先の情報連携の推進、広域避難者への情報提供の充実、市町村が作成する被災者台帳について都道府県による支援の明確化などの広域避難の円滑化と被災者支援等に当たってのデジタル技術の活用などが示されました。
今後、石川県のように県が主導して広域被災者情報データベースシステムを整備することが、全国的な標準の取組となることが想定されます。
愛知県としても、事前準備として、県や他の市町村をまたいだアセスメント情報とデータ様式の統一、標準化を含めたルールづくり等、いわゆる情報収集と共有のシステムづくりを進めるとともに、その重要性、具体的な活用イメージを分かりやすく提示しながら市町村に対して被災者支援システム導入を積極的に促す必要があると考えます。
そこで、法改正を踏まえ、被災者支援システムを導入していない県内市町村への導入促進に向けた取組についてお伺いをします。
また、大規模災害時の広域避難を想定する中で、事前準備として石川県のような広域被災者データベース・システムの整備について、その重要性に関する認識と今後の取組についてお聞かせください。
以上で壇上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◯経済産業局長(犬塚晴久君)
初めに、グローバル拠点都市のKPIについてお答えします。
第一期のKPI七項目のうち、起業人材等の輩出、起業、新規事業開発、ビジネスマッチング、資金調達の五項目で目標を上回り、売上げ規模百億円以上のスタートアップ創出、企業評価額一千億円以上のスタートアップ創出の二項目が未達となりました。スタートアップの起業と成長への支援では成果を上げた一方、大きくスケールアップするスタートアップ創出へのさらなる支援が必要となっています。
そこで、第二期では、国内市場のみならず、海外市場も見据えて事業展開するグローバルなスタートアップの育成を強化するため、当地域の海外連携事業に参画するスタートアップ数、グローバルスタートアップを目指す起業家数等をKPIに加え、グローバルなスタートアップ・エコシステム形成に向けた取組を加速してまいります。
次に、オープンイノベーションの推進についてお答えします。
オープンイノベーションに対し、受け身であったり、企業文化や事業の進め方の違いから、あと一歩を踏み出せない企業もあります。
このため、STATION Aiでは、日常的な交流コミュニティーや多種多様な交流イベントを通じ、スタートアップ同士、さらには事業会社との出会いの場を提供するとともに、コーディネーターによる伴走支援を通じ、オープンイノベーションの方針策定から協業先決定を一気通貫で支援する集中プログラムを実施しております。
こうした取組に加え、県では今年度から、オープンイノベーションの裾野拡大を目指し、事業会社の自社技術、製品の強みを生かして、スタートアップと連携するなど、新規事業を立ち上げる事業会社への支援プログラムを新たに開始しており、引き続きオープンイノベーションの推進に取り組んでまいります。
続いて、アイチ コ・クリエーション スタートアップ プログラムの取組についてお答えします。
県では、地域が主体的にスタートアップ・エコシステム形成を目指す拠点、STATION Aiパートナー拠点について、これまで東三河地域、大府・東浦地域、刈谷地域の三地域を位置づけております。
このパートナー拠点のさらなる拡大を目的に実施する本プログラムでは、スタートアップとの連携を通じて地域課題解決に取り組む実践機会の場を提供しており、これまでの先進事例を他地域にも共有し、参加自治体や支援団体の拡大を図ってまいりました。その結果、参加数は初年度二〇二二年度の九自治体三団体から、現在二十三自治体三十九団体まで拡大しており、連携の輪が着実に広がっております。
今年度からは、さらなる自治体の参画を促すため、これまで事業担当部署が中心だった参加者を、行政課題全般に関わる総務企画担当部署等にも拡大するほか、連携相手となるスタートアップの参加を大幅に増加し、マッチング機会の拡充を図ることで、県内全域でのスタートアップ・エコシステムの形成に努めてまいります。
次に、災害時のドローン利活用に向けた取組についてお答えします。
災害時の円滑なドローン利活用には、行政とドローン事業者が情報共有、連携した上で運行調整することが重要となります。
このため、県では本年三月、モビリティイノベーションプロジェクトの中に、ドローンメーカー、運用事業者などをメンバーとし、行政との橋渡し役となる愛知県次世代空モビリティ災害対応チームを立ち上げました。このチームでは、県災害対策本部を通じて、救助活動を行うヘリコプターにドローンの運行情報を提供し、相互の運行の安全を確保するとともに、被災市町村からの要請を受け、ドローン事業者を被災地に派遣するといった調整機能の構築を目指します。
今年度は、県が実施する防災訓練において、ドローン事業者と県、市町村間での迅速な情報共有、伝達の運用実証を行い、その結果を検証することにより、円滑なドローン利活用の早期実現に向け、取り組んでまいります。
◯教育長(川原馨君)
初めに、県立高校における危機管理対策の三段階チェックの修正状況及び危機管理マニュアルの運用状況についてお答えいたします。
二〇二三年三月に文部科学省から、他県における中学校への不審者侵入事案を受け、各学校設置者に対して、不審者の侵入防止対策である三段階チェック体制のマニュアルへの記載など、学校の危機管理マニュアルを点検するよう依頼がありました。
これを受け、県教育委員会では、県立高校に対して、三段階チェック体制の危機管理マニュアルへの記載と教育委員会への提出を指示し、二〇二三年度末までには、全ての学校で三段階チェック体制が記載されていること、具体的な役割分担や初動体制が記載されていることなど、実効性のある内容となっていることを確認いたしました。
二〇二四年度以降は、県教育委員会が個別に学校を訪問し、マニュアルに基づく危機管理対策が適切に行われていることを確認しております。
次に、防犯カメラの設置等危機管理としてのハード対策に対する県教育委員会の認識と今後の対応についてお答えいたします。
学校における危機管理対策において、防犯カメラは、不審者侵入の抑止や事後の検証に資する、有効な方策の一つと認識をしております。
県教育委員会が昨年度行った調査では、設置校は三十八校で、前年度から六校の増加にとどまっており、今後さらに設置を加速していく必要があると考えております。また、県立高校への防犯カメラの設置については、国庫補助の対象となっていないことから、財政措置について引き続き国に対して働きかけてまいります。
学校の危機管理対策については、ハード面による対応のみならず、来訪者の出入り管理や、教職員による定期的な巡回など、ソフト面の対応も併せて実施していくことが重要であり、こうした日々の取組を徹底し、子供たちが安心して学べる教育環境の実現に取り組んでまいります。
次に、小中学校内において教職員による盗撮などの犯罪行為が疑われる事案が発生した際の初動対応についてお答えいたします。
小中学校に対しては、被害を受けた可能性のある児童生徒の心のケアを第一に考えながら、いつ、どこで、何が起きたかの事実確認を丁寧に行うことが最も重要であり、発生直後に明らかになる事実や関係者の発言を細かに記録するよう指導しております。
また、犯罪行為である可能性が高い場合、学校は服務監督権者である市町村教育委員会に報告の上、速やかに警察と連携することも重要となります。
市町村教育委員会は、こうした学校の初動対応が適切かどうかを確認するとともに、事案全体を俯瞰して必要な助言やフォローを行う役割を担っており、事案の概略が判明した時点で、速やかに県教育委員会に報告することとなっております。
県教育委員会としましては、あま市の件なども教訓として、事案が発生した際には、児童生徒や保護者の不安が少しでも和らぐよう、学校と市町村教育委員会が、警察との連携も含めた的確な初動対応を取ることについて、改めて周知徹底してまいります。
◯保健医療局長(長谷川勢子君)
困難な事情を抱える妊婦の現状と県の認識についてお答えします。
困難な事情を抱える妊婦の方は、妊娠したことを周囲に相談できず、市町村の窓口へ行くことをためらう方が多く、その人数を把握することは難しい状況です。
本県では、二〇二三年十月からあいち性と妊娠相談ほっとラインを開設し、SNSで気軽に相談できる環境を整備しています。
昨年度は三百七十五件の相談があり、経済的な不安や育児に関する心配のほか、支援を受けたいがどうしたらいいか分からないといった声が寄せられました。こうした方々に速やかに母子保健サービスを提供していくことが大変重要であると考えております。
本県では、二〇二三年九月から、助産師が同行して市町村窓口へとつなぐ同行支援事業を実施しておりますので、引き続き関係機関と連携を図りながら、しっかりと支援してまいります。
次に、産後ケアに対する県の課題認識と今後の取組についてお答えします。
本県では、市町村の産後ケア事業の取組状況や課題を把握するため、実態調査を実施しています。
市町村からは、産後ケアを提供する助産師の資質向上を求める意見や、里帰り分娩の際に居住地以外の医療機関でも支援を受けられるよう、集合契約の導入が必要だといった意見が出されています。
これを受け、本県では、今年度新たに産後ケアに必要な専門的知識を習得するための研修を実施します。
また、集合契約については、市町村によって産後ケアサービスの内容などが異なっており、医療機関や市町村との調整が必要となりますので、愛知県産婦人科医会や県医師会などにも相談をしながら、導入に向けて検討してまいりたいと考えております。
今後も、広域調整の役割を担う県として、市町村と連携を図り、支援を必要とする方が利用しやすい環境を整備してまいります。
◯福祉局長(緒方武俊君)
自立支援が必要な妊産婦への支援体制についてお答えいたします。
本県では、支援が必要な妊産婦が、妊娠期から出産後の養育まで安定した生活を送ることができるように、市町村保健センターや女性相談支援センター、児童相談センター、福祉事務所等が支援の入り口となり、女性自立支援施設や母子生活支援施設等と連携し、各機関の専門性を生かしながら、出産前後の住まいの提供等の生活支援を行っております。
一方、国において創設されました妊産婦等生活援助事業は、支援の相談から医療機関等への同行、産前、産後の生活の場の提供までを一つの機関が包括的に支援するものでございます。
まずは、それぞれの取組の有効性や課題を明らかにするため、支援に関わる市町村や民間団体、施設、さらには先進的に取り組む他の地域の事業所等への調査を行い、困難な事情を抱える妊産婦の方々が安心して出産を迎え、母子ともに安定した生活を送っていただけるよう研究を進めてまいります。
◯防災安全局長(冨安精君)
大規模災害時における航空運用調整についてお答えをいたします。
近年の災害では様々な場面でドローンが活用され、ヘリコプターなどの航空機との迅速な運用調整が課題となっております。
このため県では昨年度から、ICTを活用して速やかに航空運用情報を共有、調整する仕組みづくりについて検討してまいりました。
また、県災害対策本部にあいちモビリティイノベーションプロジェクトに参加するドローンの運用事業者から、情報連絡員(リエゾン)を受け入れ、調整を行う訓練も行ってきたところでございます。
今年度は、航空運用情報をデジタル化するために電子ホワイトボードを導入し、具体的なオペレーションの習熟を図ってまいります。
その上で、年度内には、訓練を通じて、関係機関の間での情報共有、調整手順を検証するなど、大規模災害時に迅速な航空運用調整ができる仕組みの確立に向けて取り組んでまいります。
次に、被災者支援システムの導入促進についてお答えをいたします。
本県では、市町村に対し、防災担当課長会議等において、国の支援制度等を示しながら、システムの導入を促してまいりました。
また、国の支援対象外である住家被害認定調査等に使うタブレット端末を県が補助対象とすることで財政支援を講じてまいりました。
その結果、今年度導入を予定している十四市町を含め、合わせて県内二十九市町でシステムが導入される見通しとなっております。
そうした中、今月交付された災害対策基本法の一部改正により、市町村等に対して、被災者に関する情報の把握や提供等に当たって、情報通信技術等の活用に努めることが新たに義務づけられました。
県といたしましては、県内市町村に対して、こうした機会を捉え、改正の内容を丁寧に説明しつつ、県内市町村において被災者支援システムの導入が一層進むよう、積極的に働きかけてまいります。
次に、広域被災者情報データベースシステムについてお答えします。
能登半島地震では、石川県が作成したデータベースが活用されたと承知をしており、南海トラフ地震においてさらに広い地域で被災者の発生が想定される本県では、その必要性がより高くなるものと認識しております。
国は昨年十一月に公表した報告書において、能登半島地震における実績に基づき、情報の項目や記述方法の標準化をはじめ、今後取り組むべき課題を整理しております。
また、全国知事会においても、避難者の把握と管理に用いるシステムの標準化の必要性や都道府県域を超えた広域データベースシステムの必要性などの課題について議論が進められているところです。
県といたしましては、引き続き全国知事会と連携し、積極的な関与を国に求めることも含め、被災者情報を広域的に共有し、支援につなげることができる仕組みの構築に向けて取り組んでまいります。
◯知事(大村秀章君)
小木曽史人議員の質問のうち、スタートアップの関係について私からも申し上げます。
第二期グローバル拠点都市選定を踏まえたスタートアップ・エコシステムの取組についてお答えをいたします。
今回の選定を受けまして、中部地域が世界における最先端のモノづくりイノベーションの中心地となることを目指し、新たにメンバーに加わった岐阜県、三重県、静岡県とも連携をして、中部圏全域の産業界、大学、行政による広域都市圏型の強力なエコシステムを形成してまいりたいと考えております。
その中核拠点となるSTATION Aiには、現在約五百のスタートアップ、そして約三百三十のパートナー企業が会員となっており、このパートナー企業は当初、去年十月で二百でありましたので、もう三百三十まで増えたということでございます。それからこれまでに、これまでというのは昨日六月二十四日までに、ですから、十月三十一日グランドオープンなので、十一月から勘定して七か月、八か月弱で四百八十件を超える交流イベントが開催されております。これはピッチイベント、リバースピッチ、それからビジネスコンテスト、それからまたセミナー、フォーラム、シンポジウムといったもの、いろんな形ありますが、こういった交流イベントが四百八十を超えております。月平均六十を超えている。それぐらい使っていただいているということでございます。
また、アメリカ、フランスなど九か国、二十二の支援機関、大学との連携事業を通じまして、海外ネットワークをさらに深化、拡大させながら、海外スタートアップの呼び込みや、グローバル展開を目指すスタートアップの支援にもしっかりと取り組んでまいります。
引き続きセントラル・ジャパン・スタートアップ・エコシステム・コンソーシアムのメンバーと協力をして、世界に類例のない国際的なイノベーション創出の拠点形成に向けまして、全力で取り組んでまいります。
◯二十番(小木曽史人君)
それぞれ御答弁ありがとうございました。
スタートアップのKPIについては、その達成に向け、しっかり進捗管理をしつつ、世界をリードする取組をぜひ期待したいと思います。また、学校の危機管理、防災のDX化については、県民の命と暮らしを守るための事前に対応できる備えであるという観点から、ぜひ先送りすることなくスピード感を持って鋭意進めていただきたいと思います。
最後に、安心して子供を産み育てられる環境整備について要望をします。
まず、困難な事情を抱える妊婦の方は声を上げられないので把握が難しいとの答弁でしたが、だからこそキャッチアップできる、よりよい事業スキームをぜひ検討いただきたいと思います。
例えば兵庫県では、妊娠に特化した妊娠SOS事業を県事業として実施。三百六十五日二十四時間の相談窓口の令和六年度実績は、電話相談千九百二十六件、メール相談三百四十三件、LINE相談一万一千四百五十七件、面接五十六件に上ると伺いました。そして、その相談者のうち支援の必要性の高い妊産婦を特定妊婦等生活援助事業としてサポートする、つまり県が事業主体となって、入り口で広く的確にキャッチアップし、拾い上げた声を確実にシームレスにつなげる仕組みとなっております。
愛知県における妊娠に関する相談件数といえば、先ほど答弁にありました、例えばLINE相談であれば三百七十五件であることから見ても、悩める妊産婦を広く相談という入り口でキャッチアップできているとは到底思えません。
特定妊婦等へのサポートも、先ほど申し上げた女性自立支援施設及び母子生活支援施設、どちらも入居数に余裕があるともお聞きしているため、例えば、母子生活支援施設を一部妊産婦等生活援助事業として置き換えるなどして、妊娠期から切れ目なくサポートできる体制をつくることも可能ではないかと考えます。
出産は人生の一大イベント、特に初産の女性の多くは、その出産、子育てに少なからず不安を抱えております。悩める妊産婦さんの声なき声を拾い集め、レベルとニーズに応じた支援が確実に届く仕組みにより、安心して安全に、素直に子育てに喜びを感じられる、ひいては二人目、三人目の出産につなげられるような環境を整えていただくよう要望し、質問を終わります。